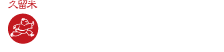第百二十三話 幻の脚本⑫
〜前号からの続き〜
13 連結屋台
2台の屋台が軒続きで連結されている。向かって左は〈弾丸ラーメン〉、右の屋台の暖簾には、いかめしい書体で〈金玉やきとり〉と書かれている。暖簾をくぐると、満席である。2つの業態が連結した屋台というのが珍しく、評判になったようだ。カウンターの山村が言った。「のぼっちゃん、ありゃあんまりやろ?」「何や」昇はずらりと並べた丼に忙しそうにスープを注いでいる。「横の屋台の名たい。アレじゃ女の客は来んばい」山村の隣のカップル客がクスクス笑っている。昇はチラリと焼き鳥コーナーを見た。全員男性客だった。しかも全員が肉体労働者風である。先日の酒をこぼした若い男もいる。「人の屋号にガタガタいうな〈コンギョクやきとり〉のどこがイカンか?黄金の弾丸ぞ。睾丸じゃなかとぞ。カッコよかろうが」丼に入れられた麺を菜箸でほぐしながら嘉子がうなづきながら言った。「そうやろう山村さん、だけんあたしゃ、せめてフリガナぐらい打ってっち言いよると」となりでは立ち上る煙に包まれて、ねじり鉢巻きの端午が忙しく焼き鳥を焼いている。きなこは笑顔で元気に接客している。肉体労働者風の客が言った。「姉ちゃん、酒もう1杯、あとダルムも3本ね」「はーい」きなこは一升瓶の栓を抜いた。屋台の外では待ち客がちらほらと並び始めた。
*(光)『焼き鳥でお酒飲んで、締めにラーメンというヨッパライの梯子コースが1軒の屋台でできるので、父ちゃんたちの屋台は評判になりました。でも焼き鳥屋台の名前といい、やっぱり父ちゃんにはデリカシーのかけらもありませんでした』
翌日の夜、焼き鳥屋台の暖簾には、下手な字で〈コンギョク〉とフリガナが打たれていた。きょうも端午兄妹は煙に包まれて忙しい。そこに山村が入ってきた。端午は顔を上げて言った。「いらっしゃい、山村さ・・・」 山村は女連れだった。易者の細川清美である。端午は清美を見て目を見張った。山村は清美を長椅子に促した。端午は横のきなこに耳打ちした。「あの美人、誰やろ?」きなこは首をかしげた。「どうしたダンゴちゃんキョトンとして、あ、そうそう、この人はそこの道頓堀(佐賀銀行久留米店の裏に当時存在した小さな飲み屋街の通称)の角の占いさん。ホソカワキヨミさんでーす」山村は宝物でも見せつけるかのように言った。端午は串を焼く手を止めたまま呆然とつぶやいた。「そ、そういえば、そん、そんな人がおったような・・・」
*(光)『ダンゴ兄ちゃんも清美お姉ちゃんに一目惚れしてしまいました』
きなこは端午の横顔を見て、それを感じ取ったようだ。手元の焼き鳥が焦げはじめた。「お兄ちゃん!焦げてる!」屋台の屋根から上がる煙がその量を増した。
翌日、端午はねじり鉢巻きの姿で、道頓堀の角にいた。清美に手相をみてもらっているようだ。端午の横にはなぜか光がいる。「そうですね、今までのあなたは仕事運が悪かったようですね・・・でもこれからは、その運はどんどん上向きになります・・・」端午は清美の顔に見とれるだけで、何も聞こえていない。そして突然切り出した。「ぼ、僕の結婚、いや、アナタの結婚、いや、アナタは結婚してますか?」光はニヤニヤしている。
*(光)『やっぱり僕はキューピットかもしれない。いたずら好きの』
3人の横を石焼き芋のリヤカーが通って行く。遠くで昇の声が聞こえた。「おーいオヤジー、芋くれーイモ!」
数日後、弾丸ラーメンの前、光は毛糸の帽子とマフラー・綿入れ半纏という完全防寒姿でいつものように歩道に絵を描いている。すると千鳥足の男が、光のチョークを持った手元を通り過ぎ、金玉やきとりの暖簾に消えて行った。酔った山村のようだ。暖簾をくぐるなり山村は端午に言った。「おいこらダンゴ!お前、清美ちゃんとこに行ったろ?」端午はあっけにとられながらも、焼き鳥の串を返している。「客として手相をみてもろうたです。それが何かイカンですか」端午はむっとして答えた。「バカタレ!客もクソもあるか、お前はただ清美ちゃんに手を触ってもらいたかっただけやろう、そうやろう、絶対そう、オレはそう思う!」山村はそのままカウンターに突っ伏し、寝言を言いだした。「オレハソウオモウ・・・キヨミチャン・・・」端午ときなこは顔を見合わせた。向こうから昇が声をかけた。「ヤマがどうかしたか?」「い、いや何でんなかです」端午は黙々と焼き鳥を焼いた。
~次号へ続く~