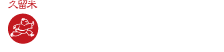第一百二十一話 映画「ラーメン侍」幻の脚本⑪
〜前号からの続き〜
12 晩 秋
弾丸ラーメンの屋台の背後には銀行のビルが並んでいる。昼はオフィス街、夜は屋台街という、2つの顔を持つ大通りである。とはいっても、歩道も車道も当時はコンクリート製だった。コンクリートは現在のアスファルトに比べ、雨に浸食されやすいのだろう、車道のあちこちに穴が空いて水溜まりになっていた。通りの向こうは西鉄久留米駅である。夜になるとほとんど車も通らないので、横断歩道もない大通りを、水溜まりを避けながらゆっくり歩いて渡れた。この一帯が、光の夜の遊び場所であった。銀行ビルの切れ間に、久留米なのになぜか〈道頓堀〉と書かれたゲートがある。小さな歓楽街の入口である。夜になると、そのゲートの下にひとりポツンと座っている女性の易者がいた。小さな台には手の平の絵が描かれたロウソクの行灯が置かれている。
光は歩道の〈お絵描き〉に遊び疲れると、よくその女性易者のところへ遊びに行った。彼女はいつも優しく光の相手をしてくれた。細くて色白の物静かなその女性は、年の頃は30ちょっと前といったところ。
*(光)『行灯のあかり越しに見るその人の笑顔は、なんとなく淋しそうでした。きなこ姉ちゃんといい、僕には何となく淋しげな大人の女性に縁があります』
「お姉ちゃん、お客さん連れてきたよ」光は無理矢理に山村を引っ張ってきた。山村は女性易者の顔をひと目見たとたん茫然としている。彼女は言った。「だめよ光ちゃん、占いの押し売りは」「いいやん、ねぇ山ちゃんおじちゃん」光は山村に同意を求めたが、山村はただ彼女を見つめている。一目惚れ状態だ。「ぼ、僕は山村秀一、さ、30歳です」
山村は緊張のあまり自己紹介をはじめた。彼女はクスリと笑って応えた。「細川清美、歳はあなたより少しだけ下です」老朽化したゲートのネオンが〈ジー〉という音を立てている。1台のオート三輪車が3人の横を走り抜けた。行灯の炎が少し揺れた。山村は清美に左手を預けたまま、清美の顔をじっと見続けている。「そうですね・・・大工さんならあと10年以内には頭領になれますよ」清美は真剣な顔で手相をみている。山村が訊いた。「け、結婚は?」「そうですね、結婚運は・・・」山村は清美の鑑定を遮って続けた。「い、いや、アナタの結婚・・・いや、アナタは結婚してますか?」「えっ」清美は顔を上げた。そして笑いながら首を横に振った。山村は満足そうに満面の笑みでうなずいた。
*(光)『僕はキューピットかもしれない』
山村はいい歳して、スキップしながら通りの向こうに消えていった。「お姉ちゃん、ぼくの手もみてくれる?」光は小さな手を差し出した。清美はその手をそっと持ったが、光の顔だけを見ながら答えた。「光ちゃんはすくすくと育ちますよ。やがて大きくなって、きれいなお嫁さんをもらって、かわいい赤ちゃんが生まれて・・・」
ほほえみながらも、なぜか清美の瞳は潤んでいた。
殆ど葉の落ちた街路樹の下を石焼き芋売りのリヤカーが通り過ぎて行く。「いーしやーきぃーもー」遠くで昇の声が聞こえる。「おーいオヤジー、芋くれーイモ。光〜お前も喰うか〜イモ!」
*(光)『父ちゃんの辞書にはデリカシーという文字はないらしい』
弾丸ラーメンのカウンターでは、隣の焼き鳥屋台〈英ちゃん〉の主人・末野英人(32歳)が昇に何やら相談している。
横には移動飲食業組合(屋台組合)の組合長・白垣猪吉(36歳)が座っている。「・・・ということで、小さいながらも店舗を持つことになって・・・」末野は言った。そこに組合長の白垣が話を補足した。「英ちゃんも嫁さんもらったきっかけに、心機一転、小さな食堂ば構えることになったったい。そこで、のぼっちゃんに相談やけど・・・、屋台仲間のよしみで、隣の英ちゃんの屋台ば買い取ってもらえんかね?」白垣はあらためて昇たちを見回した。そこには昇夫婦と櫛野兄妹の4人が立っている。白垣は言った。「しかし、従業員が増えたねぇ」「こいつらは居候たい。給料やら払うカネはなか。・・・まあ、英ちゃんと組合長が2人そろっての頼みごとなら・・・しょんなかねぇ」昇は端午兄妹を見て言った。「ダンゴときなこ、お前らやってみるか?焼き鳥の屋台」端午は答えた。「はい!アニキにいわれるコツなら何でっちゃします。」いつのまにか昇の舎弟になっている。端午は続けた。「俺、テキ屋仲間の夜店で焼き鳥も焼いとりました」「きなこは?」きなこは笑顔で答えた。「はい、喜んで!」「居酒屋かよ」昇は言った「英ちゃん、そんかわり、権利金は月賦でよかや?」「はい、喜んで」一同は笑った。
そこに山村が鼻歌交じりで入ってきた。ご機嫌である。「♪オレは待ってるぜぇ〜っち。おッ今日は満員御礼?と言っても、みんなカンケイシャかぁ」山村は酔っていた。「ほんじゃ、のぼっちゃん、宜しく頼んどくばい」白垣と末野はのれんをくぐり出た。「なんかヨカことでもあったか?」昇はコップを山村の前に置き、酒を注ぎながら言った。
「ジンセイはステタもんじゃぁない!ヒック・・・。たった一度の出会いが、ヒック、ミライへの道を大きく照らすのだぁ、ヒック」山村はカウンターに突っ伏した。昇は素早く山村のコップ酒を取り上げた。「お前はもう飲むな」昇はその酒を一気に飲み干した。
深まる秋の夜の冷気で、屋台から立ちのぼる湯気は、一段とその濃さを増していた。
~次号へ続く~