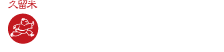第一百二十話 映画「ラーメン侍」幻の脚本⑩
〜前号からの続き〜
11 再 会
昭和20年8月9日、米軍は広島に続き、長崎に原爆を投下。まさにその日、ソ連は日ソ中立条約を一方的に破棄し、日本に宣戦布告した。日本にとっては弱り目に祟り目、ソ連は容赦なく日本領である南樺太・千島列島・満州に進行し、そこを占領した。そのとき捕虜になり、シベリアに抑留された日本の将兵・現地の日本人開拓団等の数は60万以上(一説には200万)といわれているが、抑留中の劣悪な環境と強制労働で、その多くが死亡している。その後、昭和31年の日ソ国交回復により抑留者の帰国事業が始まったが、生存した抑留者が夢に見続けてきた故郷・日本の地、そこに立つ日の訪れには、あまりに時間がかかり過ぎた。
陽の傾きで、長く伸びた板塀の影が続く小道を歩きながら、昇は櫛野に言った。
「何で父ちゃんは病院におるとか?」
櫛野は昇と肩を並べて歩いている。
「抑留中に事故で失明したとです。収容所ではまともな治療もしてもらえんやったけん」
昇は足下の落ち葉を見ながら。
「そうや・・・、娘は耳でオヤジは目か・・・」
2人の後ろに嘉子ときなこが続いている。きなこは次男をおんぶして光と手をつないでいる。
やがて、古い大学病院が見えてきた。
夕日の斜光が差し込む薄暗い病院の廊下。医者が病状の説明をしている。
「本来ならきちんと治療をすれば治っていた怪我ですよ。治療どころか、拘留中は相当劣悪な環境やったとでしょう、栄養状態も良くない。ま、これから、ちゃんと栄養をつけて、体力が戻ったら手術をしましょう。上手くいけば見えるようになるでしょう」
「先生、お願いします。手術のカネなら俺が頑張って働いて、どげんかしますけん。お願いします。お願いします」端午は医師に両手を合わせて懇願した。きなこも深々と頭を下げている。「わかりました」
病室の前で、きなこは次男を嘉子に渡した。昇たちを廊下に待たせ、櫛野ときなこの二人は病室の扉を静かに開けた。きなこは緊張している。相部屋の病室には、ひとりの患者だけがベッドに寝ていた。
父・善次郎である。目には包帯が巻かれている。
「父ちゃん」櫛野は声をかけて近づいた。すると、きなこは兄を押し退けるようにベッドに駆け寄り、善次郎の右手を両手で握りしめた。そして顔を崩しながら父の頬にすり寄った。
善次郎はつぶやいた 「み・・・みな・・・美奈子か?」。
目が見えないながらも、やはり父親である。20年ぶりでありながら、我が娘を瞬時に感じ取った。と、そのとき、きなこの喉から嗚咽の声がでた。きなこが声を出したのだ。
命を捻り、満身の力で魂の滴を絞り出したような声で、きなこは泣いた。
その声は廊下にも伝わり、長椅子でうなだれていた昇たちは、一斉に顔を上げた。
そしてついにきなこは言葉をだした。「お父ちゃん、お父ちゃん・・・」
その声の響きのなかで、廊下の3人も嗚咽した。
~次号へ続く~